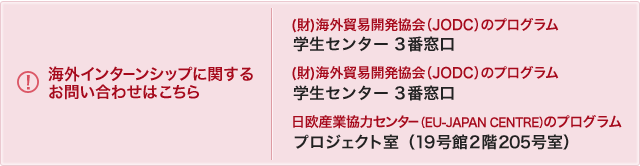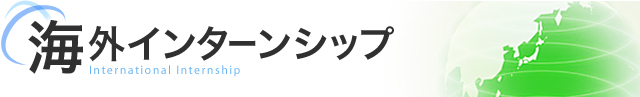- HOME
- 海外留学を希望する方へ
- 海外インターンシップ
- フィリピンでの海外インターンシップ体験記
名古屋工業大学
国際交流センター
愛知県名古屋市昭和区御器所町
TEL : +81-(0)52-735-5079
FAX : +81-(0)52-735-5587
E-mail :
ic-office@adm.nitech.ac.jp
フィリピンでの海外インターンシップ体験記
機能工学専攻博士前期課程1年 横井 悟
私は、JODCの海外短期派遣事業に応募し、2006年8月15日から8月27日まで、フィリピンにある日系企業(本社は刈谷市の株式会社サーテックカリヤ)のSURTEC PHILIPPINES, INC. において、インターンシップを行った。以下はその概要である。実習内容は、「金属メッキラインでの製造と検査、及びメンテナンスと化学分析」であった。
1.受入企業概要
(1)業種 金属メッキ、金属材料表面処理
(2)設立年月日 1996年2月2日
(3)資本金 PHP 25,100,000
(4)従業員数 204名 (2006年7月1日現在)
(5)本社の所在地 116 East Science Ave., SPEZ Laguna Technopark, Inc., Binan Laguna
(6)工場の所在地 同上
2.協力企業名
株式会社サーテックカリヤ
3.協力企業概要
(1)業種 金属めっき、金属材料表面処理
(2)設立年月日 1951年6月
(3)資本金 JPY 60,000,000
(4)従業員数 300名
(5)本社の所在地 愛知県刈谷市神明町6-100
(6)工場の所在地 同上
4.実習内容
ここでは、私がフィリピンのSPI(Surtec Philippines, Inc)で体験した実習内容について、実習した日を追いながら説明をする。私の海外就労体験の期間は2006年8月15日(火)から2006年8月27日(日)であり、この約2週間の間、SPIで大変貴重な体験をさせていただいた。
○8月15日(火)
初日はフィリピンに着いたのが昼過ぎということもあり、SPIのManager(課長職以上の方、あるいはグループチーフ(それぞれの部門の責任者))の方たちとの顔合わせを行った。Managerは坂元社長を含めて3人の日本人の他、皆現地の方なので、英語であいさつを行った。その後、坂元社長からフィリピンで日本企業の経営を行うことについて説明をしていただいた。
○8月16日(水)
本日から、本格的にSPIでの実習を行う。午前中はSPIについての説明、会社見学、そして社則の説明をしていただいた。午後からはISO14001:2004 に基づくEMS(Environment Management System [環境管理])と、ISO/TS16949:2002 に基づくQMS(Quality Management System [品質管理])について説明をしていただいた。
フィリピンには、労働者を期間工として雇用した場合であっても、6ヶ月以上雇用し続けた場合、企業はその労働者を正社員として雇用しなければならないという法律が存在する。そのため、SPIの社則ではメッキライン増設などの際に、一時的に必要となる雇用希望者をCasual (6ヶ月以内の期間工)として採用し、その期間が終了する際にやる気と能力を備えた者のみをProbationary (見習い社員)として改めて採用、一定期間が過ぎた後にRegular (正社員)としていた。さらにRegularの中でも特に能力の高い者や、日本のサーテックカリヤで一定期間の実習をこなし、知識と技術を身につけた者のみがグループチーフやManagerとなることができるという仕組みとなっていた。また頻繁に交代を強いられるCasualは、どうしても仕事や技術を覚えるまでに時間が必要なり、その間、指導を行う必要が出てくる。そこで、支給されるユニフォームを正社員はポロシャツ(Probationary:白、Regular:紺)のところ、Casualは白のTシャツとすることで、Casualの仕事状況を認識しやすくする仕組みが作られていた。多くのことが規定されている社則だが、給与として年2回、米が現物支給されるという部分を個人的には面白いと感じた。
EMS、QMSはISOで規定されているものだが、これを取得することにより企業の地球環境保全に対する取り組みや、製品の品質に対する信頼性を高めることができる。共に取得にはいくつものクリアすべき条件があるが、私は特に重要となるポイントは以下の2点で共通しているように感じた。
・自社の企業活動において、環境と製造プロセスに関しての問題点・改善案を具体的に表し、継続的に改善活動を行うこと。
・さまざまな企業活動を書類にし、いつでも確認できるように管理すること。
これらは、必ずしも簡単に取得できるものではないが、今後活動を続けていく企業には必要不可欠であり、取得は必須であるという感想を持った。
本日教えていただいた、社則・EMS・QMSがSPIを支えている土台であり、これらに基づいて様々な活動が決められているということが分かった。
本日からは実際に仕事の現場を回り、SPIで行われている実務を実習させて頂いた。
SPIの各部門と業務の流れの関係は下図のようになっている。
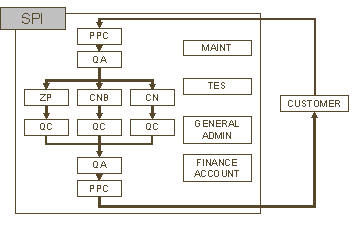
□直接商品と関わる業務
PPCが客からの被メッキ材の入庫管理をし、QAによりメッキ前品質検査を行う。実務ライン(ZP、CNB、CN)でメッキを施し、QCで全数検査を行う。再度QAでメッキ後品質検査を行い、PPCで製品の出庫管理を行う。
□その他の業務
工場内部の装置・設備の管理を行うMAINT、廃水の水質検査を行うTES、総務や経理などである。
*略称については後で説明する
○8月17日(木)、18日(金)
17日はSPIにある3種類のメッキラインのうち、ZP (Zinc Plating:亜鉛メッキ)とCNB (Cupper Nickel Barrel:銅ニッケルメッキ)を、そして18日はCN (Chemical Nickel:無電解ニッケルメッキ)の実習をさせて頂いた。 メッキの工程は大きく分けて3つに分けることができる。メッキ前工程、メッキ工程、メッキ後工程である。被メッキ材の形状、使用するメッキライン、必要とされる精度などの条件により、それぞれの工程の内容は変化するが、基本の流れとしては同じであった。
メッキの工程は大きく分けて3つに分けることができる。メッキ前工程、メッキ工程、メッキ後工程である。被メッキ材の形状、使用するメッキライン、必要とされる精度などの条件により、それぞれの工程の内容は変化するが、基本の流れとしては同じであった。
メッキ前工程は、非メッキ材を電極に接触させた状態にする作業、非メッキ材の金属表面の汚れを落とし、活性化させる洗浄作業に分けられる。
(右図は被メッキ材を電極に接触させる作業の一種でラッキングと呼ばれる作業)
メッキ工程では、メッキ液の濃度、時間、電流量など様々なパラメータを操作し、より効率的で不良率が低くなるようなメッキ環境が作り出されていた。
メッキ後工程は、メッキ材を洗浄し乾燥させ、最後に製品を電極から取り外す作業工程であった。
また、メッキ後の製品はQC (Quality Control:品質管理)により、不良がないか確認するための全数検査が行われていた。製品の数は膨大であり、傷なども大変小さいため、QCの大勢の方たちが熱心に製品に向かっていたのが印象的であった。
ZPラインの実習の際に、私を指導してくださったグループチーフが現在23歳という話を聞いて、自分と大差ない年齢の人が多くの部下を率いて仕事をしている現状を目の当たりにして、複雑な心境を覚えた。
○8月19日(土)、20日(日)、21日(月)
19日、20日は休みだった。しかし、完全に会社を休みとしているわけではなく、2交代制で休みを取っているそうだ。
また、21日もフィリピンの祝日「英雄の日」だったので休みだった。
○8月22日(火)
本日は午前中にPPC (Production Planning and Control:生産管理)を、午後からはTES [Technical Engineering Service:環境管理]を実習させていただいた。
 先にも述べたように、PPCとは被メッキ材の入庫、メッキ加工済製品の出庫を管理している部門であった。QMSにもつながることだが、いつどこで誰が製品を加工したかが分かるようにするためのトレーサビリティシステムの構築をしているのもPPCであった。PPCの実習では、SPIの顧客であるテクノエイトという会社への製品の納入、そして被メッキ材の入荷を体験させていただいた。この際、税金に関する特例措置であるPEZA認証印を忘れずに貰うことが重要となる。
先にも述べたように、PPCとは被メッキ材の入庫、メッキ加工済製品の出庫を管理している部門であった。QMSにもつながることだが、いつどこで誰が製品を加工したかが分かるようにするためのトレーサビリティシステムの構築をしているのもPPCであった。PPCの実習では、SPIの顧客であるテクノエイトという会社への製品の納入、そして被メッキ材の入荷を体験させていただいた。この際、税金に関する特例措置であるPEZA認証印を忘れずに貰うことが重要となる。
(右図は納入の際に使うトラックに載せていただき喜ぶ私)
 TESはEMSの肝となる部門であった。定期的に採取した工場廃水に対して様々な試験を行うことで、廃水中のPH、金属濃度はフィリピンの法令基準以下に保たれていた。また、TESではメッキラインからメッキ液を採取し、小型のメッキ槽で仮想的なメッキを行うことで、メッキ液の濃度を常に最適な濃度に保つ作業(ハルセルテスト)も行っていた。
TESはEMSの肝となる部門であった。定期的に採取した工場廃水に対して様々な試験を行うことで、廃水中のPH、金属濃度はフィリピンの法令基準以下に保たれていた。また、TESではメッキラインからメッキ液を採取し、小型のメッキ槽で仮想的なメッキを行うことで、メッキ液の濃度を常に最適な濃度に保つ作業(ハルセルテスト)も行っていた。フィリピンの環境基準は、日本よりも厳しいそうだ。
(右図は成分試験のひとつ:UV-VISを用いてCr6+,CN-濃度を検査する試験)
○8月23日(水)
23日は、一日かけてSPIの工場内部の装置・設備の管理を行うMaintenance部門で実習をさせて頂いた。この部門は大きく2つの業務に分けられる。1つは工場内の装置・施設を構築したり修理を行うグループ[facility]、もうひとつは工場廃水の成分を環境基準以内にする施設に対して作業を行うグループ[WWT (Waste Water Treatment:廃水処理)]である。
午前中はfacilityにて実習を行った。その際facilityの仕事には3つのタイプがあるという話を聞いた。オイル交換などの定期的なメンテナンス、故障後の修理、センサなどで定期的なデータを取り破壊予測をした上でのパーツ交換などである。
 その後、実際にfacilityで行われている業務の一部を体験させていただいた。私が体験したのは、アセチレンバーナやアーク溶接を用いてラッキング用の電極を作ったり、修理したりする作業であった。アーク溶接は以前やったことがあったのだが、うまく溶接することができず、溶接した部分から折れていくという残念な結果となってしまった。
その後、実際にfacilityで行われている業務の一部を体験させていただいた。私が体験したのは、アセチレンバーナやアーク溶接を用いてラッキング用の電極を作ったり、修理したりする作業であった。アーク溶接は以前やったことがあったのだが、うまく溶接することができず、溶接した部分から折れていくという残念な結果となってしまった。
(右図はアーク溶接によるラッキング器具の修理)
午後からはWWTの見学をさせて頂いた。
 ここは、昨日TESで検査を行った廃水を実際に排出している部門であり、TESと共にEMSを支えている。このWWTの施設には、大きな廃水用プール、何種類もの薬品、タンクなどが所狭しと並んでおり、化学プラントのようであった。
ここは、昨日TESで検査を行った廃水を実際に排出している部門であり、TESと共にEMSを支えている。このWWTの施設には、大きな廃水用プール、何種類もの薬品、タンクなどが所狭しと並んでおり、化学プラントのようであった。
ここでは、排水処理の大まかな仕組みを教えていただいた。印象に残ったのは、厳しい環境基準が、単純なフィードバック制御で達成されている点であった。また実際の現場での浄水処理は、一工程ごとに厳しい基準を設けるのではなく、全体を見て、最終的に基準を満たすことができるように処理の仕組みができていることも印象に残った点であった。
体に良くなさそうな薬品が多くあり、とても危険そうだと感じたが、会社の規定では、このような薬品を扱う際はマスク・グローブ・グラスの着用は必須となっており、安全第一がしっかり根付いているように感じた。
○8月24日(木)
本日の午前中はQA (Quality Assurance:品質保障)を実習させていただき、午後からはSPIの顧客の日本企業を会社見学させていただいた。
 QAの仕事は品質を保障、つまり良い商品のみを出荷できるようにすることだ。主な業務としては、入荷したばかりの被メッキ材の品質検査、QC後の製品の出荷前検査の2つに分けられる。検査とは言えども、ここでの検査はQCで行われる検査とは異なる。QCでの検査は、純粋に見た目のみの検査であったが、QAでの検査は数々の測定器を用いて、より品質を厳密に検査する。検査数もISOに準じているMIL TABLEに従い、一定数をサンプリングし、そのエラーのパーセンテージに応じて品質保証を行っていた。
QAの仕事は品質を保障、つまり良い商品のみを出荷できるようにすることだ。主な業務としては、入荷したばかりの被メッキ材の品質検査、QC後の製品の出荷前検査の2つに分けられる。検査とは言えども、ここでの検査はQCで行われる検査とは異なる。QCでの検査は、純粋に見た目のみの検査であったが、QAでの検査は数々の測定器を用いて、より品質を厳密に検査する。検査数もISOに準じているMIL TABLEに従い、一定数をサンプリングし、そのエラーのパーセンテージに応じて品質保証を行っていた。
ここでは、測定器の使い方と、品質保証の理論を簡単に教えていただいた。
(右図はX線を用いてメッキ厚さを測定する装置)
午後からの会社見学では、FUJITSU DIE-TECHとフィリピンTRCの見学をさせて頂いた。
FUJITSU DIE-TECHは、ATMやHDDカバーなどを主な製品としている金型会社であり、とても規模の大きな会社だった。TRCは、EPSONと強い繋がりを持ち、プリンタ用のシャフト、プラスチックのモールド品などを主な製品としている会社であった。
会社の主な製品や規模は異なっているのでもちろん会社ごとに違うことは多かったが、SPIも含めて共通していることもまた多かった。たとえば、従業員の服装である。着ている上着の色や帽子の色など、一目で作業者の職歴が分かるようになっていた。また、各社とも、女性従業員数が男性に比べて多かった。これは、フィリピンでは女性のほうが有能であるからだそうだ。
最後に、経営者の方たちの思慮の深さと見聞の広さには驚かされた。私の何気ない質問にも、自分の考えをはっきりと答えることができる力に感心しきりであった。
○8月25日(金)
SPIでの実習最終日なので、この2週間で経験したことについてプレゼンテーションを行った。初日同様、英語での発表であったが、理解していただけたようで一安心だった。
○8月26日(土)、27日(日)
会社は休みだったので、最後のフィリピンでの休日を楽しんだ。2週間は長いようで、とても短かったが、大変有意義な時間を過ごすことができた。
5.実習成果
この2週間の海外就労体験の最大の成果は、さほど遠くない将来、私が企業に就職した際に海外の工場、あるいは関連企業で働くことを以前ほど不安と感じなくなったということだろう。今までは海外の国々に対して漠然とした不安を持っていたが、その不安がある程度具体性を増して見えてきたことにより、自分の中でその不安解決の糸口を見つけることができるようになったことが、以前ほど不安でなくなった要因だと考える。
私が抱いていた漠然とした不安は、大きく3つに分けることができた。
まずは環境である。これは、生活環境や職場環境などへの不安を意味する。今回の実習を引き合いに出すと、私が2週間過ごした宿泊施設は会社に用意して頂いたものだったが、生活環境という面では十分なものであった。また、SPIは職場環境もよく整備されており、仕事がしやすそうな環境が構築されていた。
次に人である。これは生活習慣や考え方の異なる現地の方や従業員などへの不安である。SPIではさほど違和感は覚えなかったが、フィリピンでも一般的に女性の方が男性より有能であるだとか、能力のある人はより賃金の良い会社にすぐに転職をしてしまう傾向にあるなど、その国ごとの特色がある。そこで、その国の人々の考え方や常識を事前に調べておくことが重要となると感じた。
最後に言語である。これは言葉の通り、外国語への不安である。今回の実習でも、多くの英語を聞き、そしてコミュニケートしようとした。しかし相手の話している内容を満足に聞き取ることが出来ず、また伝えたいことを十分に伝えることも出来なかった。しかし、筆談、ジェスチャなどを交えることによりある程度コミュニケーションをすることができると分かった。
今回の実習から、上記のような不安を克服することに欠かせないものが何であるかについて考えた。すると、知識、勇気、努力が最も基本にあり、重要であると考えるに至った。業務に関する知識はもとより、現地に関する知識、その知識に合わせて環境を作り、そして変えていく勇気、さらに格好悪くとも何とか現地の方とコミュニケートしようとする勇気と、徐々にでもその言語を覚えていこうと努力することが重要となる。
もちろんその言語が英語となる場合は多く、また事前に学習しておく方が望ましい。そのため、これからは今以上に英語への学習に努力をしていきたいと考えた。
また、机上のみでしか知らなかったフィリピンという国、そしてフィリピンに住む人々について知ることが出来たのは、大きな成果であったと思う。
6.最後に
この2週間で多くのことを学び、そして考えさせられた。「百聞は一見に如かず」というが、人からどれだけの話を聞いても、この2週間の体験には代えられないだろう。このような貴重な体験をさせて頂きましたSPIの坂元社長を始めとした社員の方々、事前研修や連絡等でお世話になりましたサーテックカリヤの皆様、並びに多くの御足労と御支援を賜りましたJODCの皆様に心より御礼申し上げます。
どうもありがとうございました。